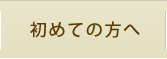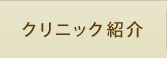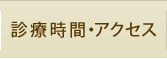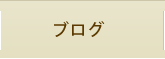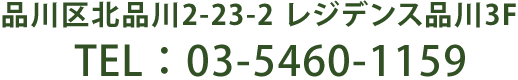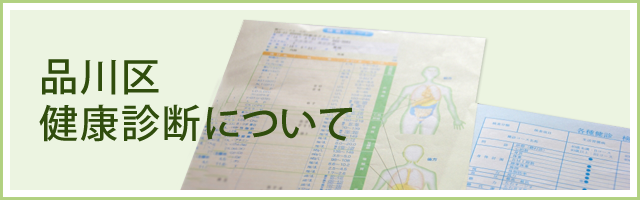咳と痰の解説
そもそも咳とは?
そもそも咳はなぜ出るのでしょう?鼻、のど、気管、気管支などの気道は呼吸に必要な空気の通り道ですが、ほこり、煙、細菌やウイルスなどの異物が入ってきたり、誤って食べ物などの異物が気管に入ってしまうことがあります。
このような異物や痰が気道にあると、気道粘膜の神経が刺激を受けて、脳にある咳中枢という場所にシグナルを伝えます。シグナルを受け取った咳中枢は、呼吸を行う筋肉に咳を出す指令を送ることで、咳を発生させます。この過程は咳反射とも呼ばれ、人が意識しないでも自動的に起こる体の防御反応といえるでしょう。
一方で咳ぜんそくやぜんそくの咳は、少し事情が異なります。これらの場合、まず発作を引き起こす刺激(ダニ、ほこり、タバコの煙など)によって気管支の筋肉(平滑筋)が縮み、その筋肉の収縮を平滑筋の中の神経が刺激として感じ取ることによって、咳中枢へとシグナルが伝わり、咳が起こります。
そもそも痰とは?
そもそも「痰」とはどのようなものか、少し解説してみたいと思います。
たんは気道から出る分泌物です。健康な人でも常に少しずつ出ていますが、普段は気道表面から再吸収されたり、のどまで上がってから無意識に飲み込まれたりしているのであまり意識されません。しかしのどの奥から肺までの空気の通り道の粘膜表面に強い刺激や炎症が長く続くと、たんが増えます。
最も多い原因は風邪ですが、通常風邪は3週間も続きません。肺炎や気管支炎でも病原菌やウイルスを排除する反応の結果としてたんがでますが、このときは発熱やだるさなどの全身症状を伴うので3週間以上診断がつかないことはあまりないでしょう。いずれにしてもせきやたんが3週間以上続くときには何か病気があると考えて呼吸器内科を受診することをおすすめします。
そして痰を伴う代表的な病気がぜんそくです。ぜんそくの痰は主にアレルギー性の炎症によるもので、粘度の高い透明~白濁であることが特徴です。またぜんそくとアレルギー性鼻炎や副鼻腔炎は合併することが多いため、このような患者さんでは鼻汁がのどにおりてくることがしばしばあり(後鼻漏といいます)、のどにおりてきた鼻汁を患者さんが痰として認識することも少なくありません。
咳の分類(期間)
咳嗽(せき)の種類についてはいくつかの考え方がありますが、代表的なのは咳がどの程度の期間続いているかです。
①急性咳嗽(きゅうせいがいそう): 3週間以内でおさまる咳
急性の咳を引き起こす原因疾患でもっとも多いのは、ウイルスなどの病原体の感染による急性上気道炎(いわゆる風邪)です。息を吸って肺に向かう空気の通り道のうち、口や鼻から咽頭(のどぼとけ)までを上気道といいます。上気道にウイルスや細菌が感染すると「急性上気道炎」の炎症が起こります。これがいわゆる風邪といわれるものです。急性上気道炎では、鼻づまり、くしゃみ、鼻水、のどの痛み、くしゃみなどの症状があります。通常であれば2〜3日で症状のピークを迎え、1週間ほどで自然に治っていきますその後咳が残ることもありますが、3週間以内におさまる場合は急性咳嗽と判断されます。
②遷延性咳嗽(せんえんせいがいそう): 3週間から8週間つづく咳
3週間以上咳が続く場合は原因として、咳ぜんそく、アトピー咳嗽、胃食道逆流、そして感染後咳嗽が多くを占めます。咳喘息やアトピー咳嗽、胃食道逆流については別の項目で詳しく解説させていただきます。なお「感染後咳嗽」は急性上気道炎が治癒した後、咳だけが残る状態でかぜ症候群後咳嗽とも呼ばれます。
③慢性咳嗽(まんせいがいそう): 8週間以上つづく咳
8週間を過ぎても咳がつづく場合は、慢性咳嗽と考え、しっかり原因を調べていく必要がありますが、実際には咳ぜんそくとぜんそくで全体の慢性咳嗽の7割を占めるというデータもあります。一方で咳が長引く場合にはまずレントゲン撮影などで肺がんや肺結核、その他の思い呼吸器の病気を除外しながら診療を進めていく必要があります。またぜんそく治療自体も専門的なスキルが必要とされることが少なくないため、当院のような呼吸器内科専門医の受診が必要です。
咳の分類(痰の有無)
別の項目で痰について述べましたが、痰が絡むかどうかでも咳を分類することができます。
①湿性咳嗽(しっせいがいそう):咳のたびに痰が伴う
- 痰を外に出そうとするため、「ゴホゴホ」と湿った咳が出ます。
- 原因として考えられるのがウイルス感染(風邪、インフルエンザ、コロナウイルス)やぜんそくや咳ぜんそく、細菌性肺炎、副鼻腔炎、気管支炎などです。また呼吸器の病気ではありませんが、心不全でも同様の症状を認めることがあります。
②乾性咳嗽(かんせいがいそう):痰なし、またはごく少量の粘液性の痰を伴う咳 →「コンコン」と乾いた咳が出ます。
- 原因として考えられるのがアトピー咳嗽、百日咳、間質性肺炎、肺がん、心因性咳嗽などです
咳の分類(痰の色)
痰が絡む咳の場合、さらに痰の色で咳の原因を考えていくことになります。
透明から白色の痰:ぜんそくや初期の気管支炎などで認められます。特にぜんそくの場合には透明な粘度の高い痰が特徴です。中には粘液栓といって、硬い白くに濁ったものがスポンと出てくるような形のものもあります。これは気管支が粘液物質でつまってしまった状態にあったものが、排出されたものです。そのため粘液栓が出たあとは、急に呼吸が楽になることもあります。
- 黄色~緑色痰:一般的な風邪(白血球がウイルスや細菌と戦った後に出てくる)のほか、肺炎や気管支炎で認められます。また副鼻腔炎でも、それがアレルギーよりも感染がメインのタイプである場合、膿のような鼻汁がのどまで落ち込んできて、やはり緑色の痰になります。
- 赤色の痰:のどや気管などが傷つき痰に血液が混じっている場合ですが、このような痰を認めた場合には肺がんや結核などの可能性があるため、すぐに医療機関を受診してください。ただし、副鼻腔炎の一部でも出血を伴い、それがやはりのどまで垂れ込んで赤色の痰になることがあります。
咳の原因
喘息・咳喘息
8週間以上つづく咳は、「慢性咳嗽」といいますが、 その原因の約40%が咳ぜんそくによるもので、ぜんそくの30%を上回るというデータもあります。実際、私のクリニックを受診されている患者さん達も同様の傾向です。いずれにしても咳ぜんそくとぜんそくを合わせて、長引く咳の原因の70%を占めるというのは、みなさんにとってはやや驚きのデータではないでしょうか?ぜんそくや咳ぜんそくについては別の項目で改めて詳細に解説させて頂きます。
しかし繰り返しになりますが、それ以外の30%のなかで特に肺がんや結核、肺炎、間質性肺炎などを見逃すことはできないため、当院では症状からぜんそくや咳ぜんそくを強く疑った場合でも、原則として(妊娠中の方などを除いて)胸部レントゲン撮影を行うことにしています。
感染後咳嗽
「感染後咳嗽」は急性上気道炎が治癒した後、咳だけが残る状態で、風邪症候群後 咳嗽とも呼ばれます。感染後咳嗽については、明確な診断基準があるとはいいづらく、実 際には遷延性咳嗽のなかでほかに原因が見当たらない場合にいきつく診断といっていいか もしれません。
アトピー咳嗽
アトピー咳嗽とは、気道の手前側の炎症がメインで、気管支の知覚神経が過敏になっている状態になって起きる病気です。喉のイガイガを伴う乾いた咳が特徴ですが、深夜から早朝に症状が出ることが多いなど、アトピー咳嗽は咳ぜんそくと区別することが難しいのが実際のところです。
区別するポイントとしてはアトピー咳嗽では咳ぜんそくとは異なり気管支拡張薬が無効であり、抗アレルギー薬の一種であるヒスタミンH1受容体拮抗薬が有効と言われています。一方で吸入ステロイド、経口ステロイド療法(症状が強い場合)を患者さんの状態によって併用することがあるなど、治療も咳ぜんそくと共通するところがあります。
副鼻腔炎
副鼻腔炎は「蓄膿(ちくのう)症」とも呼ばれ、風邪のウイルスや細菌、アレルギーなどにより、副鼻腔の粘膜に炎症が起こることで発症します。風邪(ウイルスや細菌感染)やアレルギーなどがきっかけで鼻の中で炎症が起きると、鼻の粘膜が腫れたり、ドロッとした鼻水が出てきたりします。それにより副鼻腔と鼻の間の通路がふさがると、副鼻腔に分泌物や異物がせき止められてしまい、鼻水や膿がたまって発症するのが副鼻腔炎です。
症状としては「食事の匂いがよくわからない」「鼻がつまる」「ねばりのある鼻水が出る」といった症状のほか、頭痛や集中力の低下などがみられる場合もあります。また鼻水がのどにまわる「後鼻漏」や、副鼻腔の粘膜にポリープ「鼻茸」(はなたけ)ができることが多いのも特徴です。
副鼻腔炎は、発症から4週間以内の場合は「急性副鼻腔炎」、症状が3ヵ月以上続く場合は「慢性副鼻腔炎」と診断されます。
慢性副鼻腔炎は、炎症を起こしている部分に集まっている細胞(白血球)の種類によって、大きく2種類に分けられます。昔は“好中球”という細胞が多い非好酸球性慢性副鼻腔炎が主流でした。しかし最近では“好酸球”という細胞が多い、新しいタイプの慢性副鼻腔炎が増えてきました。この慢性副鼻腔炎は「好酸球性副鼻腔炎」と呼ばれ、国の指定難病に指定されています。好酸球性副鼻腔炎は、非好酸球性副鼻腔炎とくらべて治りにくく、再発しやすいことが問題となっています。ここでお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、この好酸球はぜんそくの発症にも深く関係していることをすでにお伝えしています。
近年,アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎・せんそくを基本としておなじ気道系のアレルギー性炎症のメカニズムと診療をひとまとめのものとして考える「one airway, one disease(一つの気道、一つの病気)」という考え方が広く定着してきています。ぜんそくと好酸球性副鼻腔炎の関係性も、まさにその一端と言ってよいでしょう。両社は密接な関係なだけに、ぜんそく患者の40%~73%に慢性鼻副鼻腔炎を合併し、慢性副鼻腔炎患者の約20%はぜんそくに罹患しているといわれます。好酸球性副鼻腔炎は治りにくいのが特徴で、2015年から難病指定されています。
COPD
COPDはタバコの煙などの有害なガスを長い年月にわたって吸い込むことによって、空気の通り道である気道(気管支)が狭くなったり、気道の先端にある肺胞(酸素と二酸化炭素の交換を行う組織)が壊れたりしてしまう疾患です。そのため、酸素を吸って二酸化炭素を排出する「ガス交換」の効率が悪くなり、息切れが起こるのです。40歳以上の8.6%、約530万人の患者さんがいると推計されていますが、その多くは未だにCOPDと診断されず適切な治療も行われていません。
COPDの最大の原因はタバコです。喫煙者の15〜20%が発症するといわれることから、「タバコ病」とも呼ばれています。なおCOPDの発症には加齢も重要な影響を及ぼすことから、通常COPDは40歳以上の方に見られる病気と言われています。
たばこの煙を吸い込むと、肺や気管支が炎症を起こして咳や痰が出たり、気管支が細くなり空気の流れが悪くなったりします。さらに、気管支の奥にある肺胞が壊れてしまうと肺気腫が発生します。COPDではこれらの変化が両方とも起こっていると考えられ、残念ながら治療によって元に戻すことはできません。
特徴的な症状は、体を動かしたときに起こる息切れです。はじめは階段を上るときに起こしていたのが、悪化すると平地を歩いても息切れするようになります。これは心不全にも似た症状ですが、そもそもCOPDと心不全は合併することが非常に多い疾患同志といえます。いずれにしてもこのような症状を認めた場合は、受診を強くお勧めします。
胃食道逆流
胃食道逆流症は、胃内容物や胃液が食道へ逆流して起こり、胸やけや食道炎を中心とした逆流症状が生じ、慢性の咳の原因にもなることもあります。
ちなみに胃食道逆流は中高齢の女性に多く、ぜんそく患者さんのGERD保有率は45~71% と一般より高く、合併しているとぜんそくが重症化しやすいといわれています。私自身、クリニックでぜんそくの患者さんを診察していると、胃食道逆流症を合併していることが多いことに気づきます。
胃食道逆流は基本的には胸やけなどの症状に基づいて診断し(そのための質問票もあります)、胃酸の分泌を協力に抑える薬剤の内服を開始します。多くは薬物療法で改善しますが、この病気はタイプによらず暴飲暴食、早食い、喫煙、アルコール多飲、姿勢の悪さ、就寝前3時間以内の食事などの生活習慣が発症原因のことが多々あります。このようなケースでは薬物療法と並行して原因となる生活改善を行っていくことが必要です。
いずれにしてもこのような症状を認める中高年以降の方は食道がんや胃がんのスクリーニングのためにも、定期的に胃カメラの検査を受けていただくことをおすすめしています(当院では胃カメラを実施していないため、連携医療機関にご紹介させていただいております)。
気胸
気胸とは何らかの原因により肺から空気が漏れることで、肺が潰れてへこんでしまう病気です。突然の胸痛で発症し、呼吸困難を伴うこともあります。
軽症であれば安静を保つことで自然治癒を望むこともできますが、一方で血圧低下や非常に重い呼吸障害が見られ、緊急の対応が必要になる緊張性気胸と呼ばれるものもあります。そのため、気胸では重症度を正確に評価し、迅速な対応につなげることが重要です。
自然気胸が代表的であり、肺のう胞(ブラと呼びます)というもともと弱くもろい部分が破れて起こる気胸です。肺嚢胞が破れる特定のきっかけはなく、どのようなときでも起こる可能性があります。たとえば、激しい運動をしたからといって発症するわけではなく、寝ているときにでも発症することもあります。自然気胸は、背の高くて痩せている20歳前後の男性に発症しやすい傾向にありますが、それは身長が伸びる際に肺もそれに伴って引っ張られ、その結果多くは肺の先端部分がもろくなり、肺のう胞になると考えられています。
自然気胸は胸部X線撮影で診断できます(非常に軽度の気胸は、胸部CTで初めて診断されることもあります)。
軽度の場合は、外来通院で経過観察することが可能です。中等度以上の場合には胸腔ドレナージと言って、局所麻酔下に身体の表面から胸の中に向けてドレーンという直径6~7mmの管を入れて、溜まった空気を体の外に出す治療を行います。これによりしぼんだ肺を膨らませて、穴が自然にふさがるのを待ちます。しかし、空気漏れの原因となった部分に再び穴があくことも多く、再発率は30~50%といわれています。そこで、空気漏れがなかなか止まらない場合、自然気胸が2回以上再発している場合、また気胸の再発をなるべく避けたい場合には、手術を選択することになります。
肺炎
通常、単に「肺炎」という場合は、感染症による肺炎のことを指すことが多いため、ここでもそれを「肺炎」として解説したいと思います。
肺炎の初期症状は、発熱、咳、痰(黄色や緑色)ですが、これらは風邪でも見られる症状です。しかし7~10日以上も咳が続く、高熱が続く、息が苦しい、息を吸うと胸が痛いといった状態であれば、風邪ではなく肺炎の可能性があります。症状が長引く場合は、医療機関を受診しましょう。ちなみに風邪の場合は、鼻やのどのいわゆる上気道に病原微生物が感染して炎症を起こしますが、肺炎は文字通り肺の中の感染症であり、主には肺胞という部位に炎症が起こります。肺は、肺胞というブドウの房のような形をした、ごく小さな袋がたくさん集まってできています。それが肺胞です。
通常であれば、細菌やウイルスなどの病原微生物を呼吸器の防御機能が排除しますが、慢性疾患(たとえば糖尿量など)やストレスなどのために免疫力が落ちているときに肺炎が起こしやすくなります。
また加齢による影響も大きく、年をとるとともに病気に対する抵抗力(免疫力)も低下し、肺炎のリスクが大きく増加します。
一方で、高齢者の場合、発熱や咳、痰など典型的な症状がはっきりあらわれないことが多く、肺炎と気づかないうちに重症化する危険性があります。
肺炎の診断は、症状や経過の確認、身体所見、血液検査、胸部X線撮影、胸部CT撮影などを総合して行います。血液検査では炎症反応が上昇し、胸部X線写真や胸部CTでは肺炎を起こしている部分がスリガラス影や浸潤影と表現される肺内の白い影として写ります。また、病原体(原因菌やウイルス)を調べるために尿や血液、のどのぬぐい液の抗原・抗体を調べたり、痰の中の菌を培養して調べたりすることも治療のうえで重要となります。
原因により異なりますが、細菌が原因と考えられれば抗菌薬を用いて治療します。ウイルスが原因であれば抗ウイルス剤を用いる場合もあります。
誤嚥性肺炎
誤嚥性肺炎とは、唾液や飲食物などが誤って気管に入り、それと一緒に細菌などが肺に入り込むことで起こる肺炎です。そのため大きくくくればいわゆる肺炎の一種なのですが、誤嚥性肺炎のみで統計をとっても死因の上位に入ってくる病期です。そもそも肺炎で亡くなる人のほとんどは、65歳以上の高齢者であり、高齢者の肺炎の多くが、『誤嚥(ごえん)性肺炎』が原因と言われています。
高齢者の方は、気管に入ったものを咳で外に出す力が弱くなったり、飲み込む力が弱くなっているため、誤嚥が起こりやすくなります。
誤嚥するのは飲食物に限りません(気道異物)。夜寝ている間にわずかずつ唾液が気管に流れ込むことがあり、唾液内に肺炎球菌などの細菌が含まれていると肺炎を起こすことがあります。
誤嚥性肺炎の診断は基本的には先ほどお話した肺炎と同様です。
また治療も原因菌に対する抗菌薬を用いた薬物療法が基本となります。全身状態や呼吸状態が悪い場合には入院して治療をします。
抗菌薬は肺炎の原因となる菌に効果があり、炎症を鎮めることができますが、誤嚥自体を防ぐ効果はないため、治療後に誤嚥を起こすと再び発症する可能性があります。したがって、誤嚥性肺炎では日々の口腔ケアによって口の中を常に清潔に保つことが重要です。なぜなら普段のケアによりら口の中の細菌の量を比較的少なくしておけば、もし唾液を誤嚥したとしても、肺炎になるリスクを下げることができるからです。一方で誤嚥自体を防止するためのリハビリテーションを行うことも大切です。
間質性肺炎
通常の肺炎は肺胞の中で起こるとお伝えしましたが、間質性肺炎は、肺胞の壁に炎症が起こり、正常な構造が壊れ、線維化が起こる病気です。肺胞の壁を通して人は酸素を体内に取り込んでいるのですが、この壁が硬く、厚くなるために、それだけ酸素が通過するのが大変になってしまい、身体の中に酸素が取り込みにくくなってしまいます。
初期は無症状のことも多いですが、進行すると労作時の息切れや空咳(痰を伴わない、乾いた咳)などの症状があらわれます。
代表的な原因は、リウマチなどの膠原病ですが、それ以外に塵肺、薬剤性のもの、健康食品や漢方、サプリメントなどが原因によるものなどさまざまな間質性肺炎が報告されています。
しかしもっとも多いのは原因不明の「特発性間質性肺炎」です。間質性肺炎の80〜90%を占め、そのなかでも一番多いのが「特発性肺線維症」(I P F)です。50代の男性に多く、そのほとんどが喫煙者です。
診断に関しては問診や聴診をしたうえで、胸部レントゲン撮影や胸部CT検査などの画像検査、血液検査、呼吸機能検査などを行います。
肺がん
肺がんは、肺の気管支や肺胞の一部の細胞がなんらかの原因でがん化したものです。肺がんは日本においてはすべてのがんのなかでもっとも年間の死亡者数が多いがんです。肺がんの最大の原因(特に男性の場合)はタバコですが、喫煙のほか、受動喫煙、環境、食生活、放射線、薬品なども肺がんの原因として挙げられています。
肺がんの一番特徴的な症状は血痰ですが、必ずしも認められる訳ではありません。肺がんの初期症状は、ほかの呼吸器疾患の症状と区別がつかないことも多く、なかなか治りにくい咳や胸痛、声がれなどがみられる場合には医療機関の受診をおすすめします。このような症状があって受診し胸部Xp検査を行った場合や、健診や人間ドックでレントゲン撮影を行った場合に、肺に肺がんの可能性を示唆する影を認めた場合にはさらに胸部CT撮影を行います。そこで肺がんが強く疑われた場合、総合病院に紹介のうえ肺がんが疑われる部位から細胞や組織を採取する病理検査を行い、これにより本当にがんかどうか、がんの場合はどのような種類のがんであるかを調べ、診断を確定することになります。
結核
肺がんは、肺の気管支や肺胞の一部の細胞がなんらかの原因でがん化したものです。肺がんは日本においてはすべてのがんのなかでもっとも年間の死亡者数が多いがんです。肺がんの最大の原因(特に男性の場合)はタバコですが、喫煙のほか、受動喫煙、環境、食生活、放射線、薬品なども肺がんの原因として挙げられています。
肺がんの一番特徴的な症状は血痰ですが、必ずしも認められる訳ではありません。肺がんの初期症状は、ほかの呼吸器疾患の症状と区別がつかないことも多く、なかなか治りにくい咳や胸痛、声がれなどがみられる場合には医療機関の受診をおすすめします。このような症状があって受診し胸部Xp検査を行った場合や、健診や人間ドックでレントゲン撮影を行った場合に、肺に肺がんの可能性を示唆する影を認めた場合にはさらに胸部CT撮影を行います。そこで肺がんが強く疑われた場合、総合病院に紹介のうえ肺がんが疑われる部位から細胞や組織を採取する病理検査を行い、これにより本当にがんかどうか、がんの場合はどのような種類のがんであるかを調べ、診断を確定することになります
非結核性抗酸菌(NTM)症
細菌の中に抗酸菌というグループがあるのですが、その中で結核菌、らい菌を除いたものを非結核性抗酸菌と呼びます。非結核性抗酸菌は英語の表記の頭文字をとって、NTMとも呼ばれます。NTM200種類以上の菌が含まれ、土や水、家畜を含む動物など環境中に生息しています。NTMはさまざまな臓器に感染しえますが、最も多い感染臓器は肺で、NTMによる肺の感染症を肺NTM症と呼んでいます。かつては結核の人やもともと肺に病気をもつ人の免疫力が低下した場合に起こりやすいといわれていましたが、近年は、肺に病気がなく免疫力が正常な人にも増加していると報告されています。
NTMは結核と異なり、人から人に感染することはありませんから、その点は安心してください。
肺非結核性抗酸菌(肺NTM)症特有の症状はありません。咳や痰をきっかけに見つかることもありますが、症状はなく偶然に検診の胸部レントゲンやCT検査で見つかることもあります。気管支に病変を作るので、血痰が出たり、病気が進行すると疲れやすさや体重減少がみられたりすることがあります。
病状により薬剤治療を検討することもありますが定期的に胸部レントゲン撮影を行いながら経過を観察していくことも多い病気です。なお前述のように土や水回りに存在する菌であるため、その点に関しての生活習慣指導も重要なポイントになります。
肺血栓塞栓症
肺血栓塞栓症は、なんらかの原因で、肺動脈という肺と心臓をつなぐ血管が血栓などで詰まると、肺の血流が落ちて酸素が肺から供給されなくなることで発症する、最悪の場合は命にかかわる病気
よく知られているのは、長時間狭い座席に座ることで、太ももやふくらはぎの深い静脈の血流がうっ滞して血栓(血のかたまり)ができ、さらに血栓が肺に流れて、肺血栓塞栓症が生じるいわゆる「エコノミークラス症候群」です。ほかにも大きな手術の後や寝たきりになると発症しやすくなります。高齢者が自宅で座りっぱなしの生活をつづけていると、脚の血管に血栓ができ肺血栓塞栓症を起こすことがあります症状は、咳、急に始まる呼吸困難や息切れ、胸の痛みがよくみられる症状です。冷や汗が出たり、胸がドキドキする、呼吸の回数の増える、背中の痛み、血の混ざった痰、発熱などを認めることもあります。
このような事態を避けるためには肺血栓塞栓症の主たる原因である深部静脈の血栓症を予防することが重要です。例えば、海外渡航時のフライト中、同じ姿勢で長時間過ごすと足の血流がうっ滞して、足の血栓が生じやすくなります。十分に水分を摂取すること、2~3時間に1度は歩行することをおすすめします。
心因性咳嗽
咳が続いていて、詳しく検査を行いこれまで挙げてきたような病気が否定されたとしても、咳だけが長びいて治らないとい場合があります。そのようなケースではストレスが密接に関与している心因性咳嗽の」可能性を考えます。
心因性咳嗽の特徴は、
- 急性の咳がでる風邪、気管支炎などの感染症や、呼吸困難や喘鳴(ぜんめい)、咳嗽が出現する気管支ぜんそく(ぜんそく)などとは異なり、痰(たん)がからまないコンコンという乾いた咳が慢性的に続くこと(3カ月以上)
- 季節に関係なく起こり、日中に起こることが多く睡眠中にはほとんどなく、また何かに集中している時には全くでないこと
- いろいろな検査をしても咳がでる身体的な原因がみられないこと
- 治療の経過で咳止めの薬、炎症を抑える薬、抗生物質などの薬は効果がなく、抗不安薬や抗うつ薬および各種の心理療法が効果を発揮すること
以上のことからその発症と経過には何らかのストレス(心理社会的因子)が関与しているなどです。
現代においては皆がさまざまなストレスを抱えて生きているといえますが、最も見逃せしてしまっていけないポイントとしては、欲求不満や葛藤があるにもかかわらず、常に自分の嫌な感情を抑えてまで周りの期待に応えようと過剰な適応努力をしている人に起こった咳が、その人の感情の抑圧のはけ口になって慢性の咳となり持続することです。
治療としては心療内科の先生の力をお借りして必要に応じて薬物治療を含めた治療を行うほか、ストレスマネージメントの方法を指導してもらうこともあります。もちろん入浴、適度な運動、十分な睡眠などのストレスの解消も重要です。
クリニック概要
- クリニック名
- 医療法人社団M-FOREST みやざきRCクリニック
- 診療科目
-
- 内科
- 呼吸器内科
- アレルギー科
- 睡眠時無呼吸症候群
※当院では小学生以上の診察とさせていただいております。
- 住所
- 東京都品川区北品川2-23-2 レジデンス品川3F
- アクセス方法
- 京急本線 新馬場駅北口より徒歩2分
TV TOKYO天王洲スタジオより徒歩5分 - 電話
- 03-5460-1159
- ACCESSMAP
- 診療時間
-
月 火 水 木 金 土 日祝 午前 高岡 小山 宮崎 宮崎 第2,4週宮崎
第1,3,5週休診①白畑
②交代制- 午後 宮崎 宮崎 飯塚 濱邊 宮崎 - - 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日の時間:
受付時間:午前9:00から12:45、午後14:15から18:00
診療時間:午前9:15から12:45、午後14:30から18:00
土曜日の時間:
受付時間:午前9:00から12:45
診療時間:午前9:15から12:45
2025年4月より一部医師の変更がございます。
※土曜日の交代制の医師について、第4週以外は呼吸器内科の滝澤医師、第4週は呼吸器内科の笹田医師になります。