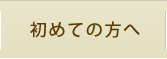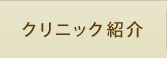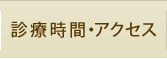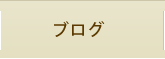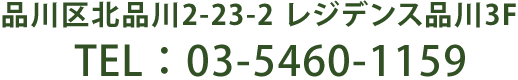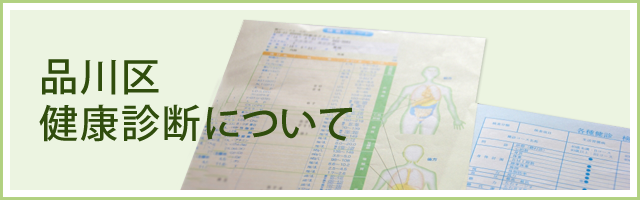小児喘息と大人喘息
喘息の治療
喘息の合併症
喘息の解説(基本編)
そもそも喘息とは?
当院に受診、通院されている患者さんの多くがぜんそくもしくは咳ぜんそくと言ってよいと思います。国内で約1000万人もの患者さんがいらっしゃると考えられるぜんそくですが、ぜんそくのメカニズムというは決して画一的ではありません。一人一人のぜんそくの成り立ち、いわば個性とでもいうべきものがものすごくバラエティーに富んでいるのがこの病気の大きな特徴の一つでもあります。
当院を受診された患者さんには、気管支ぜんそくを①「気管支が敏感になって咳が出やすくなっている状態、また②「空気の通り道である気管支が収縮することによって、息苦しさを感じる状態です」ということをお伝えしています。これは共通する場合がほとんどだからです。
ぜんそくの正体は、気道の慢性的な炎症です。気道に炎症があると過敏になり、ダニやほこりなどの刺激でぜんそくの発作が起こります。発作とは、気管が狭くなって咳が出たり、呼吸困難を起こすことです。
残念ながらぜんそくの診断は簡単ではありません。高血圧や糖尿病のように数値だけをもって診断をくだすことはできず、主治医があなたの症状やこれまでの経過を確認し、場合によってはいくつかの検査を行って、総合的に判断します。
症状の特徴
以下の項目当てはまる場合にはぜんそくの可能性が比較的高いと考えられます。
- どちらかというと夜や明け方に症状が悪化する。
- 風邪をひいたあとに、咳症状が長引くことが多い。
- 以前ぜんそくの吸入薬を使用したことがあり、症状が改善したことがある。
- 小児喘息だった。
- アトピー性皮膚炎やアレルギー性鼻炎がある。
実際には非常に多くの確認項目がありますが、これらが代表的なポイントになります。これらの症状にお心あたりのある方は是非当院までご相談ください。
喘息のタイプ
アトピー型喘息
アレルギー反応が気道で起こるとアトピー型ぜんそくになりますが、皮膚の場合はアトピー性皮膚炎、鼻の場合はアレルギー性鼻炎そのためこれらの病気はとても似たグループの病気ということができ、最新の治療では共通して使用される薬剤もあります。
アレルギーによって引き起こされる病気においては、まず問題となっている特定の物質(アレルゲン)を回避する環境整備がとても大切で、吸入ステロイド、気管支拡張剤など薬剤治療と同時に取り組む必要があります。
たとえばエアコンや洗濯機などの家電製品には、機械の内部に湿気を多く含むことでカビの増殖につながるものがあります。これらは目につきにくいので、エアコンのフィルターをこまめに洗浄したり、洗濯槽のカビ取りをするなど、カビをなるべく増やさないように心がけましょう。
また犬や猫などのペットの抜け毛やフケは、アレルゲンとなりやすく、かつダニが増える原因となります。ペットを遠ざけることが、ぜんそくの改善にもっとも効果がありますが、それは避けたいですよね。その場合は、寝室を一緒にしない、こまめにシャンプーをする、室内やケージの清掃を怠らないなどの工夫が必要です。
非アトピー型喘息
アレルギーが原因ではないぜんそくが「非アトピー型ぜんそく」といいます。血液検査などを行っても、アレルギー原因がはっきりしない患者さんに多くみられ、多くが成人の患者さんです原因として次のものがあります。
- 風邪やインフルエンザなどのウイルス感染症
- 気候の変化(寒暖差、気圧、湿度)
- 過労やストレス
- 肥満
- 運動(運動誘発ぜんそく)
- タバコの煙
なかでも、ぜんそくを発症させるものでもっとも多いのが、ウイルス感染症です。私のクリニックの問診項目にはこれまでご紹介したものも含めて多くの項目がありますが、その中に「風邪をひくたびに、咳が長引くことが多くありませんか?」という質問があります。この項目にチェックが入る場合は、ぜんそく体質である可能性が高いと考えられます。
小児喘息と大人喘息
小児喘息の特徴
小児ぜんそくの特徴して次の傾向が挙げられます。
- 男の子に多い(男児は女児の1・5倍多い)
- 90%以上がアトピー体質
- 生まれつき気管支が敏感
- 生まれたときの体重が少ない
- 肥満がある
- 遺伝的な体質をもつ
症状のポイント
- 泣いたり不機嫌になったりすることが多くなった。
- かぜをひくたびに咳が続く。
- 呼吸するときに「ぜーぜー」「ひゅーひゅー」と音が出る。
- 遊びまわって遊んだあとに咳が出始める。
- 夜間や早朝に苦しそうに咳をする。
お子さんはは大人と違って苦しさを言葉でうまく伝えることができないことも多いですから、このような様子がないか注意してみていただければと思います。
小児喘息の特徴
小児ぜんそくは2~3歳までに60~70%が、6歳までに80%以上が発症するといわれています。その後、思春期になると症状が軽快するひとも多いですが、約30%が大人喘息に移行すると言われています。しかし一度ぜんそく症状を完全に認めなくなった50~70%の小児ぜんそく患者さんのうち、30%弱が成人になって再発するといわれています。
小児ぜんそくは思春期になると症状が軽快しつつも、約30%が成人喘息に移行するとされています。一方、症状が消失した50~70%の小児喘息患者のうち、30%弱が成人になって再発するとも言われています。そのため成人でぜんそくを抱えている患者さんのうち一定割合は小児ぜんそくの持ち越し、もしくはぶり返しといわれています。
大人(成人)喘息の特徴
原因がアレルギー以外のことも多い
小児ぜんそくの90%以上がアレルギー性です。このようなぜんそくが「アトピー型ぜんそく」です。
一方で、大人ぜんそくでは血液検査で成人ぜんそくのアレルゲンを発見できるのは60%ほどです。残り40%はアレルゲンを発見できない「非アトピー型ぜんそく」と言われています。
根治は難しい
小児ぜんそくでも、そのまま大人になっても持ち越してしまう方、大人になってぶり返してしまう方が一定数いらっしゃるため、全員が治る訳ではありません。一方で、大人ぜんそくの方は基本的に完治は難しいというのが正直なところです。非アトピー型が多いことやぜん息悪化の要因が小児よりも多いためです。また大人ぜんそくは小児ぜんそくよりも治療が難しいこと少なくありません。
*ぜんそくは、高血圧症や糖尿病と同じように慢性疾患と捉え、治すというより、長期にわたってしっかりコントロールしていく必要がある病気です。
一方で、小児ぜんそくがなく成人になって初めてぜんそく症状が出現する人(ここでは大人ぜんそくとして解説していきます)は、成人のぜんそく患者さんの70~80%を占め、そのうち、40~60歳代での発症が60%以上を占めると言われています。
私のクリニックでもまさにこのような年代の方々が、「生まれて初めてぜんそくと言われた」「ぜんそくは子供がなるものではないのか?」「おとなになってからぜんそくの初めてなるなんて!」と仰ることが多いですね。ただ、このデータをご覧いただければ、決して珍しくないことがお分かりいただけると思います。
実際大人の方のぜんそく患者さんは年々に増えており、2017年の調査では成人の10.4%が喘息症状を患っているという結果が出ています。
喘息の治療
喘息の薬物治療
ぜんそくが疑われるとき、ぜんそくの治療を行ってみましょうというと、「確実な診断もついていないのに薬を投与するの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、高血圧や糖尿病などのように、数値などで明確に診断できる病気と違って、喘息治療においてはこのような「診断的治療」から始めるしかないのです。
吸入ステロイドと気管支拡張薬の配合剤を使用して症状が改善するかレントゲン撮影を行って肺炎などの異常を認めず、また問診からぜんそくが疑われた場合は、吸入ステロイド薬と一緒に、長時間作用性抗コリン薬(以下、LABA)という気管支拡張薬(気管支を広げる薬)を処方して、3日以上様子をみます。この時点で明らかな反応がみられれば、ぜんそくと診断することになります。反応がない場合は、他の疾患の可能性も考えますが、なかにはぜんそくであっても初期治療の薬が足りずに反応を確認しづらかったり、治療反応を認めるまでの日数にもある程度のばらつきがあることがあり、医師は総合的に判断します。
アトピー型ぜんそくでも非アトピー型ぜんそくでも、治療の基本は吸入ステロイドと気管支拡張薬です。しかし「非アトピー型ぜんそく」はアトピー型ぜんそくよりもメカニズムが複雑であることも多く、中にはステロイド治療の反応が悪く、その他の抗アレルギー薬や、場合によっては一部の抗生物質を少量ずつ長期に内服する、やや特別な治療を行うこともあります。
また、従来の薬剤治療を行っても改善が不十分であるときには、生物学的製剤と呼ばれる特別な治療を行うこともあります。当院では喘息に用いられる生物学的製剤をすべて取り扱っております。
日常生活の中で出来ること
ダニやホコリを減らす環境整備特にアトピー型のぜんそくの方にとってはハウスダストやダニなどのアレルゲンををいかに避けるかが重要になってきます。
そうじの徹底など、対策にとり組みはじめてから「あ、発作が起こらない」「コントロールできている」という自覚症状の改善に至るまで数か月かかることも珍しくありません。そのため粘り強いとり組みが必要です。
しかし、「薬はなるべく減らしたい」と思われる方の助けになっているケースも多く見られます。炎症の原因となる悪化因子への対策を行う環境整備によって、薬を減らすための有効的な手段となります。
習慣にするコツは「3」です。行動科学における「3の法則」では、3日間つづけば継続力がついてくるといわれています。
3週間つづけば習慣になり、3か月間つづけば結果が出てくるといいます。
高すぎる目標は、挫折の原因になりやすいので、すぐにできそうなところからはじめていきましょう。
- ほこりを通さないマットレスカバー、布団カバー、枕カバーを使用する
- ダニに発育を抑制するためにお部屋の湿度を50%以下にする(ただし40%以下になると、ウイルスにとって有利な環境になるので乾燥し過ぎにも注意してください)
- そうじ機を1m²あたり20秒ほどかける
- シーツ、パジャマなど、こまめに洗濯する
- 身の回りにできるだけ毛羽立つものを置かない(毛足の長いカーペット、ぬいぐるみ等)
これらの対策は通年性のアレルギー鼻炎の方や、アトピー性皮膚炎の方にとっても有効です。
喘息の解説(発展編)
咳喘息
咳ぜんそくは,ぜんそくの一種、もしくは喘息の前段階と言ってよい病気です。いわゆる典型的なぜんそくとの違いとしては喘鳴や息苦しさを伴わず、咳のみが唯一の症状であること、などが挙げられますが、炎症の本態はぜんそくと共通であることも多く、むしろ無理に喘息と分けて考えなくてもよいのではないかと思います。
私がこのように言うのにはもう一つ理由があり、咳ぜんそくとお伝えした場合に患者さんによってはむしろ「私はぜんそくではない」という必ずしも正しいとは言えない認識に至ってしまうリスクを感じるためです。
そのため学問的にはぜんそくと咳ぜんそくは区別されるべきものであっても、一般的には両者は同じグループの病気なのだと理解していただくのが良いのではないかと思います。実際ぜんそくと咳ぜんそくは同様の治療を行います。また咳ぜんそくの30~40パーセントが典型的なぜんそくに移行すると言われていますが、ぜんそく同様の治療を行うことでその移行率を低下させることできます。
妊娠中の喘息
妊娠中にぜんそく症状が、軽くなる方が1/3、変わらない方1/3、悪化する方が3分の1ずつ認められています。また、ぜんそく患者さんが妊娠すると、今まで行なっていたぜんそく治療を中断してしまうケースもみられます。
妊娠中はホルモンバランスが大きく変化し、つわりで体調がすぐれなかったり、お腹が大きくなることによる通院の大変さ、ぜんそくの治療薬が胎児に悪影響を及ぼすのではないかという不安、妊娠によるストレス増加など、さまざまな要因が考えられます。
しかし、妊娠中でもぜんそく治療を決して中断してはいけません。ぜんそくをしっかりコントロールしないと、次のようなさまざまなリスクが高まります。
妊娠中にぜんそく治療をしないリスク
- 妊娠合併症の最大の原因は、ぜんそく発作による低酸素血症
- 低酸素血症によって胎児に重大な影響を与える。
- 低出生重児の増加、早産、死産のリスク上昇
- 妊娠合併症の要因となる色々な合併症(妊娠中毒症など)の増加
このように治療でコントロールしないと、ぜんそく発作の頻度が増えるとともに、母体と胎児への影響も増してしまいます。一方でぜんそく治療薬の多くが妊娠中でも安全に使用できますのでご安心ください。妊娠中も治療をしっかりつづけることで母体、胎児双方の健康を守ることができます。また安全な分娩時にもつながっていきます。
高齢者の喘息とCOPD
COPDについては別の項目で触れていますが、COPDを合併するとぜんそくが重症化しやすくなり、一方でぜんそく合併によりCOPDが重症化するという、ある意味負のスパイラルに陥ってしまい呼吸機能が著しく低下してしまいます。しかしぜんそくとCOPDは治療も似ているため、しっかり治療を行うことで状態を改善することが可能です。
また年齢と共に狭心症などの心臓病を抱えている方も増えてきます。これらの方がぜんそく発作を起こしてしまうと、もともと心臓の余力が小さいところに低酸素状態が加わるため、さらに状態が悪化してしまいます。そのため普段から心臓病、ぜんそく双方の治療をしっかり行う必要がありますが、ぜんそくの治療薬が心臓に若干の悪影響を与える場合、一方で心臓病の治療薬がぜんそくにやはり多少の悪影響を与える場合もあるため、心臓病の専門家である循環器内科医と呼吸器内科医がしっかり連携して治療にあたる必要があります。
そもそも高齢になると、免疫力が低下しやすく、ぜんそくを悪化させる大きな要因となる風邪やインフルエンザ、肺炎など呼吸器の感染症に罹りやすくなります。
症状が急激に悪くなる「急性増悪」を招くと、死に直結するリスクが高まってしまいます。予防のためには、インフルエンザが流行する前に予防接種を受けましょう。また、肺炎を予防するためにも、「肺炎球菌ワクチン」の接種を受けることが有効です。いずれのワクチンも自治体からの補助を受けられるケースが多いので、ぜひお住いの自治体に問い合わせてみてください。
アスリート喘息
ぜんそくの方の中には、普段はぜんそくの症状がないのに、運動時だけぜんそく症状が出る方がいらっしゃり、このようなぜんそくを運動誘発性ぜんそく呼びます。
アスリートの場合、強度の高い運動により過換気状態になることで肺に強い負担がかかり、より運動に誘発される気管支の収縮を起こしやすいとされます。また過酷な呼吸環境が反復されることにより、気管支粘膜のダメージが蓄積することも原因と考えられています。
ちなみに一般人とアスリートを比較した場合、アスリートの方がぜんそくの頻度が高いと言われていて、オリンピックに参加した日本代表選手の中で8~12%の選手がぜんそくを持っていたという報告もあります。
種目別でみると夏季は自転車競技、ヨット・カヌー、冬季ではクロスカントリー、アルペンスキー、スケート競技競技が代表的ですが、特に耐久種目や冬季種目の選手がぜんそくを抱えていることが多いとされています。
運動誘発性喘息の治療についてお話しましょう。
基本的には通常のぜんそく治療と変わりはありません。
薬物療法
- 吸入ステロイド薬を毎日使用する
- 運動/競技前に気管支拡張薬(SABA)を吸入する
- 抗アレルギー薬の1種である、ロイコトリエン拮抗薬を毎日服用する
非薬物療法
- マスクを着用し、乾燥や冷気を予防する
- 十分なウォーミングアップを行う
- アレルゲンや大気汚染物質の飛散する環境での練習を避ける
- 風邪などの感染症にかからないように予防策を取る
- 脱水を予防する
なお、喘息の治療薬の多くは除外措置(TUE)申請なく使用できますが、一部ドーピング禁止薬に当たる薬もあります。そのため、気管支拡張薬の一部や喘息発作の時に使用するステロイド全身投与は大会前に使用する場合はTUE申請が必要となりますので、事前にご相談ください。
職業性喘息
「実はぜんそく患者が多い職業があります」。
特定の労働環境のもとで、特定の職業性物質にさらされることで発症するぜんそくを「職業性ぜんそく」といいます。仕事日に症状が悪化し、休日には軽快するようであれば職業性ぜん息の可能性が高いと言えるでしょう。
たとえば看護師、医師、ゴム手袋を使用して調理する職業の方などのぜんそくは、ラテックスが原因物質となっています。
化粧品会社の美容担当者、理容師では、人のフケでぜんそくを起こしたり、ブリーチする際に使用する過硫酸塩、酸化染料のジアミンの略称で知られるパラフェニレンジアミンでぜんそくになることが報告されています。
職業性ぜんそくの原因となる物質はさまざまあります。煙や塩素などの刺激物質と、アレルギー反応を引き起こす原因となる感作物質に分けられます。さらに分子量の違いから、高分子量物質と低分子量物質に分けられます。このような物質を吸入し続けることで、ぜんそくの状態に至ってしまうのです。
治療に関しては、通常のぜんそくと同じですが、やはり環境整備が重要であるため、場合によってはお勤めの会社などに可能な対応策について相談する必要も出てきます。
アスピリン喘息
アスピリンぜんそくは大人ぜんそくの一種で(小児においては稀)、アスピリンをはじめとする解熱鎮痛薬(ロキソニン、ボルタレンなど多くのメジャーな薬剤が含まれます)を服用したときに、非常に強いぜんそく症状と鼻症状を引き起こす体質を有する方を、アスピリン喘息(解熱鎮痛薬ぜん息)と呼びます。詳しいメカニズムは不明ですが、解熱鎮痛薬全般に過敏な体質をもっている喘息患者さんに発症すると考えられています。成人喘息患者さんの約5~10%にみられ、男性の2倍の割合で女性に多いとされています。難治性の副鼻腔炎の中には、特にこのアスピリンぜんそくを合併していることが多くあり、注意が必要です。ぜんそくの方が解熱鎮痛薬の内服に関して一般的に注意が必要とされているのは、このアスピリンぜんそくである可能性が否定できないためです。しかしタイプの薬剤過敏性はその時の体調によって症状が出現したりしなかったりするものではないため、裏を返せば普段ロキソニン等の一般的な解熱鎮痛薬を使用していて上記のような症状を認めたことがない方は、ぜんそくであっても問題なくこれらの薬剤を使用できると言ってよいと思います。
一方で、アスピリンぜんそくの方のこれら薬剤への過敏体質は、原則的に一生続くとされています。そのため、喘息の症状がよくなっていても、注意が必要です。しかしアスピリンぜんそくの方がほぼ安全に使用できる薬剤も存在しますので、アスピリンぜんそくを指摘されている患者さんは必ずご相談ください。
喘息の合併症
アレルギー性鼻炎・花粉症
アレルギー性鼻炎は、アレルゲンが鼻粘膜から侵入すると免疫反応が起こり、鼻水や鼻づまり、くしゃみなどの症状が引き起こされる病気です。代表的なアレルギー性鼻炎は、春(スギ、ヒノキ)と秋(ブタクサ等)の花粉の飛散する時期に、鼻汁やくしゃみ、鼻のかゆみで発症する「花粉症」が挙げられます。また、一年を通して鼻症状がある「通年性アレルギー性鼻炎」では、代表的なアレルゲンであるハウスダストやダニ以外に、カビやゴキブリも原因となることがあり検査が必要です。
治療の第一歩はアレルゲンの回避ですが、薬物治療も重要です。各種抗アレルギー薬の内服に加えてステロイドを含めた点鼻薬の使用も有効です。また、近年はアレルギー免疫療法(舌下免疫療法もしくは減感作療法とも呼びます)も長期的な効果を示す有効な治療法として注目されています。
ちなみにぜんそくの人の60~80%にアレルギー性鼻炎の合併がみられるといわれていますし、一方でアレルギー性鼻炎患者の20〜~30%にぜんそくが合併しているという調査結果もあります。
乳児期、医師に診断されたアレルギー性鼻炎と診断されると、11歳までにぜんそくを発症するリスクが2倍になるという報告もあります。一方で、アレルギー性鼻炎を治療すると、ぜんそくの症状が改善することも知られています。
大切なことは、ぜんそくの治療だけでなく、鼻炎にも注意を払いながら治療を検討するということです。やはり鼻と気管支は「one airway, one disease(一つの気道、一つの病気)」なのだということが、ここでもおわかりいただけると思います。
アトピー性皮膚炎
アレルギー反応が気道で起こるとアトピー型喘息になりますが、皮膚の場合はアトピー性皮膚炎、鼻 の場合はアレルギー性鼻炎になります。そのためこれらの病気はとても似たグループの病気ということができ、最新の治療では共通して使用される薬剤もあります。アレルギー疾患のある家族がいる場合、小児ぜんそくになる可能性が高くなります。また、両親ともにぜんそくの場合、子どもがぜんそくを発病する確率は、両親ともぜんそくでない場合の約5倍、アトピー性皮膚炎の場合もおよそ同様の確率とされています。
また、気管支ぜんそくやアレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎等のアレルギー疾患のうち1つにかかると、他の(残り2つの)アレルギー疾患も合併している可能性があります。
アトピー性皮膚炎をお持ちの方で咳が出る方も、一度ぜんそくの可能性を考えて専門医を受診してみたほうがいいと考えています。
睡眠時無呼吸症候群
2024年、日本人の閉塞性睡眠時無呼吸の中等症以上の方の約40%にぜんそくが見られたという研究結果が、川崎医科大学呼吸器内科学の小賀徹氏らによって発表されました。
閉塞性睡眠時無呼吸は、上気道に空気が通る十分なスペースがなくなり、寝ている間に呼吸が止まってしまいます。夜間のいびきや日中の眠気など、さまざまな症状が生じます。
著者らは、「ぜんそくと閉塞性睡眠時無呼吸の合併は過小評価されている」として、ぜんそくの治療効果を高めるためにも閉塞性睡眠時無呼吸の合併がないか治療時に検査することを推奨しました。睡眠時無呼吸症候群の国内の潜在患者数は900万人程度と推測するデータもあり、特に中高年以上の男性や閉経後の女性はリスクが高まります。ご家族から「寝ているときに息が止まっていることがある」と言われたり、普段から大きないびきを指摘されている方は一度検査を受けてみることをおすすめします。睡眠時無呼吸症候群を放置すると、脳梗塞や心筋梗塞、認知症のリスクを高めることにもなってしまいます。
クリニック概要
- クリニック名
- 医療法人社団M-FOREST みやざきRCクリニック
- 診療科目
-
- 内科
- 呼吸器内科
- アレルギー科
- 睡眠時無呼吸症候群
※当院では小学生以上の診察とさせていただいております。
- 住所
- 東京都品川区北品川2-23-2 レジデンス品川3F
- アクセス方法
- 京急本線 新馬場駅北口より徒歩2分
TV TOKYO天王洲スタジオより徒歩5分 - 電話
- 03-5460-1159
- ACCESSMAP
- 診療時間
-
月 火 水 木 金 土 日祝 午前 高岡 小山 宮崎 宮崎 第2,4週宮崎
第1,3,5週休診①白畑
②交代制- 午後 宮崎 宮崎 飯塚 濱邊 宮崎 - - 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日の時間:
受付時間:午前9:00から12:45、午後14:15から18:00
診療時間:午前9:15から12:45、午後14:30から18:00
土曜日の時間:
受付時間:午前9:00から12:45
診療時間:午前9:15から12:45
2025年4月より一部医師の変更がございます。
※土曜日の交代制の医師について、第4週以外は呼吸器内科の滝澤医師、第4週は呼吸器内科の笹田医師になります。